| あなたは累計 |
|
人目の読者です。 |
| あなたは累計 |
|
人目の読者です。 |
 ogata@hiroshima-u.ac.jp
ogata@hiroshima-u.ac.jp
ご意見をこちらのBBSへどうぞ.
第1巻第1号 2001年1月
第1巻第2号 2001年2月
第1巻第3号 2001年3月
第1巻第4号 2001年4月
第1巻第5号 2001年5月
編集前記
ICFA/PAC報告 渡辺貴弘(東大院工・原施) 6/26
6/26
ビーム物理研究会入会案内
会合
プロシーディングス
ネットでお勉強
この「通信」は絶えず更新を繰り返し,月末にその結果をバックナンバーとして残すことにしています.この6月号は,6月初旬は5月号とほとんど同じですが,月末にはだいぶ変わったものとなり,その変わり果てた姿が,保存版としての6月号となります.原稿は1ヶ月から2ヶ月掲載されます.
 6/26
6/26ICFA(Beam Dynamics Workshop on Laser-Beam Interactions, 6/11-15,State University of New York, Stony Brook, NY) では5日間にわたり短パルスX線発生などを中心に発表・議論がなされました。 PAC (Particle Accelerator Conference, 6/18-22, Chicago, Illinois) では同じく5日間、粒子加速器全般にわたり広く大量に発表がありました。 現在私は短電子パルスの時間軸分布の計測を行っているのですが、これについて もいくつか発表がなされたので(マイナーな分野ですが)以下に少し具体的な内容を 書きます。
以前より、ピコ秒からフェムト秒電子パルスを計測する手法は数多く提案されていま
す。
これらを大まかに分類すると、
・ストリークカメラ
・電子の放射するコヒーレント光を干渉・分光する手法
・RFにより電子パルスを直接高速にキックし、空間分布に変換する手法。
・電子の通過時の電場をピックアップし、解析する手法。
・その他の手法(例:インコヒーレント放射の統計的ノイズを解析する手法)
今回もRFでキックする手法、コヒーレント放射としてSmith-Purcell放射を
用いた手法(電子がGratingの近くを通過した際に放出される放射の角度分布や
スペクトルなどからパルス幅を導出する手法)などが発表されました。その多く
は理論としてはフェムト秒オーダーに達していますが、実際に計測してパフォー
マンスを確認することも大切だと感じました。
PACではアト秒の電子パルス発生法(理論)に関する発表もあり、短パルス
計測法の開発の必要性は高まっているようです。
一方、短パルスX線の計測法については専らストリークカメラ(時間分解能
:数百フェムト)のようです。
アカデミックな話からは少しそれますが、両者の会議を通じて発表形式の
変化を感じました。皆さんご存知の通り、最近はコンピュータとプロジェクタ使った
口頭発表、および大型プリンタを用いて1枚の奇麗な紙に印刷されたポスター
発表が増えてきています。今回の2つの会議ではこれらを使った発表の方が
主流を占めていました。作る側としては好みは分かれると思いますが、聞く側
としてはうまく作成された発表はやはり聞きやすいと思いました。
以上、簡単ですがICFAとPACの報告です。
入会を希望する方は申し込み書に記入して、世話人会に申し込み、その承認を得てください.入会申し込み書の記入事項は、
1)姓名、同ローマ字綴り、
2)生年月日
3)勤務先、職名、就学先、学年、所在地、e-mail、現住所、紹介者名(世話人2名)です。(世話人の紹介を得られない場合は、世話人会に直接入会を要請してください。この場合、入会希望者は世話人会の要求する資料を提出してください、面接をお願いする場合もあります。)
連絡はmailto:SOKEN@BAROQUE.KEK.JPへお願いします.
■6/18-22 PAC2001 Chicago, Illinois.
■6/24-29 International Workshop on 2nd GENERATION PLASMA ACCELERATORS, Presqu'ile de Giens, France. 日本からの参加者急募とのこと.
■7/4-6 総研大・KEK 夏期実習 素粒子原子核・物質構造科学・加速器科学, KEK.
■6/30-7/21 SNOWMASS Snowmass, Colorado.
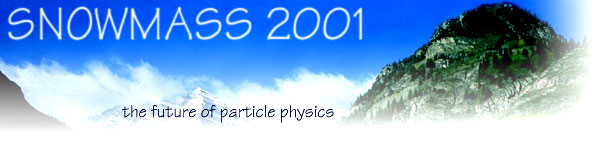
■8/1-3 第26回 リニアック技術研究会 つくば.
■8/7-8 原子力分野における加速器の研究開発ワークショップ ‐21世紀における加速器・ビーム科学の研究開発の在り方‐ 京都大学原子炉実験所. 6/15
6/15
サーキュラーより.....近年の加速器・ビーム科学分野の広がりは目覚しいものがある。本年開始された原研‐KEKの統合プロジェクトを始め、国の大型プロジェクトは多数進められており、また産業・医療における発展は著しい。このような動きは今後どのような方向に向かうのであろうか。またこのような大きなうねりを支える人材の養成、特に大学の教育研究体制はどのようになっているであろうか。今回、我が国の加速器・ビーム科学の研究開発を支えている20を越える研究機関から研究者が集まり、特に原子力の視点からこの分野の現状を認識するとともに今後の研究開発の進め方について議論するためにワークショップを開催することになった。各界の方々のご出席と討論への参加を期待する。
■8/27-30 OHO'01高エネルギー加速器セミナー「大強度陽子加速器技術」高エネルギー加速器研究機構 6/18
6/18
十数人の講師陣! 締め切りは7/27あるいは,定員になりしだい.
■9/17-21 APAC01 Beijing.
■10/15-19 23rd Advanced ICFA Beam Dynamics Workshop on High Luminousity e+e- Colliders Cornell Univ., Ithaca, NY.
■10/29-31 第13回加速器科学研究発表会 大阪大学コンベンションセンター
論文賞あり.「日本は昔加速器で元気だった」話から始まる「日本の加速器の歴史(仮題)」の招待講演や,懇親会における最近公開された,戦争直後の「サ
イクロトロンの破壊」のビデオの
放映企画があります.
■2002/3/11−16 International Symposium on Science of Super-Strong Field Interactions 原研関西研.
以下の会合のプロシーディングスがpdf形式でダウンロードできます.
■第25回リニアック技術研究会 7/12-14/2000 SPring-8.
以下のビーム物理の教科書がpdf形式でダウンロードできます. すでにホームページに教科書を掲載していて,ここに取り上げても良いという方はご一報下さい.
■町田慎二 Space Charge Effects http://hadron.kek.jp/member/machida/pub/pub.html
■鎌田進 ビーム物理学入門 http://www-acc-theory.kek.jp/members/kamada.html
■平田光司 "Advanced Single Particle Dynamics" (RIKEN Winter School on Physics of Beam)(1998) (日本語:単粒子力学上級編) http://www-acc-theory.kek.jp/members/HIRATA.html
■小方厚 レーザー・プラズマ・ビームの相互作用 http://home.hiroshima-u.ac.jp/~beam/ogata.html
■J. Rosenzweig " Fundamentals of Beam Physics" http://www.physics.ucla.edu/class/00W/150_Rosenzweig/notes/index.html,著者はUCLAのBeam Physics Labの教授.