| あなたは累計 |
|
人目の読者です。 |
| あなたは累計 |
|
人目の読者です。 |
 ogata@hiroshima-u.ac.jp
ogata@hiroshima-u.ac.jp
ご意見ご提案をこちらのBBSにどうぞ.
第1巻第1号 2001年1月
第1巻第2号 2001年2月
第1巻第3号 2001年3月
編集前記
HEACC報告 平田光司 (総研大)
物理学会年会 ビーム物理セッション報告 岡本宏巳
(広大AdSM), 中島一久 (KEK加速器/総研大), 野田 章 (京大化研)
ビーム物理研究会入会案内
高エネルギー物理学奨励賞の募集
会合 4/23
4/23
プロシーディングス
ネットでお勉強
この「通信」は絶えず更新を繰り返し,月末にその結果をバックナンバーとして残すことにしようと思いますが,いかがでしょうか. この4月号は,4月初旬は3月号とほとんど同じですが,月末にはだいぶ変わったものとなり,その変わり果てた姿が,保存版としての3月号となるはずです.
ところが近年、PAC,EPAC,APACなどの「加速器国際会議」が開かれるようになる中で、HEACCの 存在意義を疑問視する意見が広汎に見られるようになった。このきっかけとなったのは1995年に PACとHEACCが同時開催となったことと思われる。HEACCはPAC で置き換え可能なものと認識され るようになり、PACとEPACで十分な上にAPACまで始まって、忙しくてしょうがない、というのが 一般的な感覚なのであろう。
このためC11ではICFAにHEACCのありかたについて諮問し、ICFAではHEACC中止の意見が大勢を しめる状況となった。当時DESYの所長で あったB.WiikはHEACCを中止すべきで無い、という意見だったようで、ICFAの小委員会として HEACC検討委員会を設けDESYのF.Willekeを委員長とし、国際委員会を設立した。Willeke委員会は、 HEACCを高エネルギー加速器に焦点をしぼった専門性の高い小規模な会議として存続すべしとの答 申を行い、今回のHEACCはその線にそって企画された始めてのものである。
会議の内容は、現在稼動中(KEKBなど)、建設中(LHCなど)、近未来計画として検討中(TeVリ ニアコライダー、ミューオンコライダーなど)の高エネルギー加速器、また将来の加速技術(レー ザー・プラズマ加速など)についての包括的なレビューである。これは理論的、技術的な問題点を 高エネルギー物理学コミュニティーの共通の認識として把握することを目的としたものであるが、 狭義の高エネルギー物理学(実験、理論)コミュニティーからの参加がほとんど得られなかったの は残念である。
狭義の高エネルギー物理学コミュニティーが加速器を切り離そうとする傾向が近年強まっているようで、実際、ICFAは以前の合意を翻し、「メジャーな高エネルギー物理学の研究所が次回開催地のスポンサーとして得られない場合、 ICFAはHEACCを中止する意向である」と菅原KEK機構長(ICFA議長)から発表された。これらの反 HEACC的な動きを受けて、HEACCプログラムの一環として「HEACCの将来について」の討論会が もたれた。PAC,EPAC,APACにHEACCを解消する意見は少数で、むしろ高エネルギー物理学コミュ ニティーの重要な会議として、実験、理論との関係を強める方向で現在のHEACCを存続させるべき だとの意見が大勢をしめた。
私見であるが、理論、実験の研究者が高エネルギー加速器の将来を他人事のように感じているよう な現状では、高エネルギー物理学に将来は無いであろう。根本的な意識変革が必要とされる。
全体的な印象をいくつか。ビーム物理セッションが正式に設けられたのは今回が初め
てであったが、丸2日分の講演申し込みがあって、その意味ではまずまずの成果が上
がったように思う。ただその一方で、個人的には、加速器の周辺機器開発に関する発
表が主体であったような印象が残り、基礎物理的な話題の提供がもっとあっていいの
ではと感じた。また、加速器開発の話は色々とあったのに、肝心のビームダイナミク
スに関する話はほとんど無かった。そもそもKEKからの参加者が少なかったのは、
HEACCと完全に日程が重なってしまったからであろう。たしか昨年も、物理学会と加
速器関係の国際会議のスケジュールをオーバーラップさせていたように思うが、今後
は注意すべきである。
岡本宏巳(広大AdSM)
入会を希望する方は申し込み書に記入して、世話人会に申し込み、その承認を得てください.入会申し込み書の記入事項は、
1)姓名、同ローマ字綴り、
2)生年月日
3)勤務先、職名、就学先、学年、所在地、e-mail、現住所、紹介者名(世話人2名)です。(世話人の紹介を得られない場合は、世話人会に直接入会を要請してください。この場合、入会希望者は世話人会の要求する資料を提出してください、面接をお願いする場合もあります。)
連絡は
ビーム物理研究会SOKEN@BAROQUE.KEK.JP
へお願いします.
hecforumで『第3回(2001年度) 高エネルギー物理学奨励賞 推薦及び応募のお知らせ』 を御覧になっった方も多いと思います。過去の受賞例を見ても狭い意味の高エネルギー物理にこだわらず、質の良い加速器研究であれば受賞の可能性もおおいにあります.以下はhecforumからの抜粋です.
『第3回(2001年度) 高エネルギー物理学奨励賞 推薦及び応募のお知らせ』
下記の要領で 「第3回 高エネルギー物理学奨励賞」の 対象候補者と論文の推薦及び応募の受け付けを行います。
- 記 -
1. 推薦・応募締切 :2001年 4月30日
2. 対象者及び論文:1998年 4月 1日より2001年 3月31日の
間に公表された論文(博士論文は正式審査を通過した時点、他の論論文は雑誌に掲載もしくは
プレプリントが発行された時点とする。)で公表時
の対象者の年齢が35才以下であること。
3. 推薦・応募手続き:推薦・応募用紙に必要事項を記入し、
対象論文の別刷りまたはコピー 、推薦状(推薦の場
合)、論文要旨(日本語100〜200字程度)そ
れぞれ6部とともに下記に 送付・提出のこと
4. 提出先 :高エネルギー物理学研究者会議事務局
>
5. 発表 : 2001年6月末、HECFORUM にて発表
推薦・応募用紙は
http://www.icrr.u-tokyo.ac.jp/CRC/sokuhou/sokuhou-073.txt
にあります.
■ 5/17-18
ミニワークショップ 「小型逆コンプトン散乱x線源」 核燃料サイクル開発機構 大洗工学センター. 4/23
4/23
■6/11-15 ICFA Beam Dynamics Workshop on Laser Beam Interactions State University of New York, Stony Brook, NY.
■6/18-22 PAC2001 Chicago, Illinois.
■6/24-29 International Workshop on 2nd GENERATION PLASMA ACCELERATORS, Presqu'ile de Giens, France.
■7/4-6 総研大・KEK 夏期実習 素粒子原子核・物質構造科学・加速器科学,
KEK.  4/23
4/23
■6/30-7/21 SNOWMASS Snowmass, Colorado.
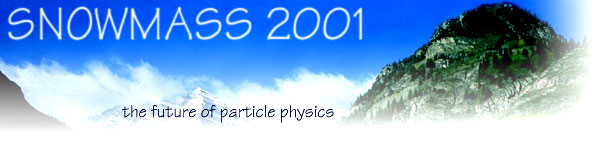
■8/1-3 第26回 リニアック技術研究会 つくば.
■9/17-21 APAC01 Beijing.
■10/15-19 23rd Advanced ICFA Beam Dynamics Workshop on High Luminousity e+e- Colliders Cornell Univ., Ithaca, NY.
■10/29-31 第13回加速器科学研究発表会 大阪大学コンベンションセンター
■2002/3/11−16 International Symposium on Science of Super-Strong Field Interactions 原研関西研.
以下の会合のプロシーディングスがpdf形式でダウンロードできます.
■第25回リニアック技術研究会 7/12-14/2000 SPring-8.
以下のビーム物理の教科書がpdf形式でダウンロードできます. すでにホームページに教科書を掲載していて,ここに取り上げても良いという方はご一報下さい.
■町田慎二 Space Charge Effects http://hadron.kek.jp/member/machida/pub/pub.html
■鎌田進 ビーム物理学入門 http://www-acc-theory.kek.jp/members/kamada.html
■平田光司 "Advanced Single Particle Dynamics" (RIKEN Winter School on Physics of Beam)(1998) (日本語:単粒子力学上級編) http://www-acc-theory.kek.jp/members/HIRATA.html
■小方厚 レーザー・プラズマ・ビームの相互作用 http://home.hiroshima-u.ac.jp/~beam/ogata.html
■J. Rosenzweig " Fundamentals of Beam Physics" http://www.physics.ucla.edu/class/00W/150_Rosenzweig/notes/index.html, 著者はUCLAのBeam Physics Labの教授.