| あなたは累計 |
|
人目の読者です。 |
| あなたは累計 |
|
人目の読者です。 |
ご意見ご提案をこちらのBBSにどうぞ.
編集前記
研究会報告 弥生研究会 上坂 充
(東大 工 原施)
ビーム物理研究会入会案内
会合
プロシーディングス
ネットでお勉強
この「通信」は絶えず更新を繰り返し,月末にその結果をバックナンバーとして残すことにしようと思いますが,いかがでしょうか. この3月号は,3月初旬は2月号とほとんど同じですが,月末にはだいぶ変わったものとなり,その変わり果てた姿が,保存版としての3月号となるはずです.
プログラムはこちら.

本標題の研究会としては2回目で、約80名を参加者を得て盛会であった。
短パルスビーム応用のセッションでは、国内では初めてであろうGaAsのミクロダイナミクス研究の発表を集め、横断的議論をした。普段は異なる学会や研究会で活動されている研究者が一同に会し、活発な情報交換がなされた。具体的には、時間分解X線回折で格子の動き、レーザー照射による電子状態変化、レーザー照射による電子や遠赤外線(THz光)の発生、分子動力学数値解析の最先端の研究報告があった。それらの現象は相互に密接に相関し合っている。それぞれの分野の方々に有効な情報が供給されたと実感している。特にまず初めに起こる電子ダイナミクスとそれに引き続き起こる格子ダイナミクスとの繋ぎが今後の課題であろう。極短レーザー照射下のGaAs格子変化による高速X線スイッチの開発などは、ポンプ&プローブ分析の能動的デバイス開発への新展開であり、特記すべきことである。また新たな研究協力への展開も議論された。
ビーム物理セッションでは主にレーザーフォトカソード高周波電子銃の国内の最新研究成果、計画、研究協力の講演がなされた。Sバンド高周波電子銃開発に関しては、極限性能を目指した国際産官学の研究協力体制が整いつつあり、アメリカを近いうちに追い越す気配が感じられた。また関連して、電子顕微鏡用電子銃、FEL用新型電子銃、Xバンド高周波電子銃、非線形レーザーコンプトン散乱の報告もあり、有効な情報交換がなされた。電子顕微鏡用電子銃のフォトカソード化のような斬新な提案もあった。このように我が国でも様々な先進電子銃開発は各所で活発に実行されており、21世紀の加速器科学に明るい見通しが感じ取れた。
昨今パルスX線(SR、レーザー励起)発生・利用の短期研究会が盛んになってきている。その中で本弥生研究会は、それらの情勢を睨みながら、的確かつタイムリーなテーマを取り上げて、今後も企画運営していく所存である。
最後に、今回の弥生研究会は平成13年1月1日に発足したビーム物理学会初の共催研究会であったことを付記する。
入会を希望する方は申し込み書に記入して、世話人会に申し込み、その承認を得てください.入会申し込み書の記入事項は、
1)姓名、同ローマ字綴り、
2)生年月日
3)勤務先、職名、就学先、学年、所在地、e-mail、現住所、紹介者名(世話人2名)です。(世話人の紹介を得られない場合は、世話人会に直接入会を要請してください。この場合、入会希望者は世話人会の要求する資料を提出してください、面接をお願いする場合もあります。)
連絡は
ビーム物理研究会SOKEN@BAROQUE.KEK.JP
へお願いします.
■6/11-15 ICFA Beam Dynamics Workshop on Laser Beam Interactions State University of New York, Stony Brook, NY.
■6/18-22 PAC2001 Chicago, Illinois.
■6/24-29 International Workshop on 2nd GENERATION PLASMA ACCELERATORS, Presqu'ile de Giens, France.
■6/30-7/21 SNOWMASS Snowmass, Colorado.
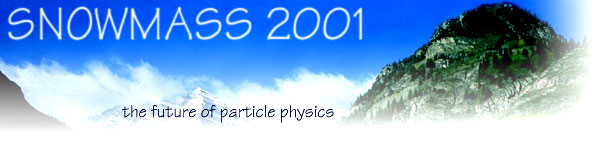
■9/17-21 APAC01 Beijing.
■2002/3/11−16 International Symposium on Science of Super-Strong Field Interactions 京都関西原研 総合大学院大学の湘南レクチュアとのジョイント
以下の会合のプロシーディングスがpdf形式でダウンロードできます.
■第25回リニアック技術研究会 7/12-14/2000 SPring-8.
以下のビーム物理の教科書がpdf形式でダウンロードできます. すでにホームページに教科書を掲載していて,ここに取り上げても良いという方はご一報下さい.
■鎌田進 ビーム物理学入門 http://www-acc-theory.kek.jp/members/kamada.html
■平田光司 "Advanced Single Particle Dynamics" (RIKEN Winter School on Physics of Beam)(1998) (日本語:単粒子力学上級編) http://www-acc-theory.kek.jp/members/HIRATA.html
■小方厚 レーザー・プラズマ・ビームの相互作用 http://home.hiroshima-u.ac.jp/~beam/ogata.html
■J. Rosenzweig " Fundamentals of Beam Physics" http://www.physics.ucla.edu/class/00W/150_Rosenzweig/notes/index.html, 著者はUCLAのBeam Physics Labの教授.